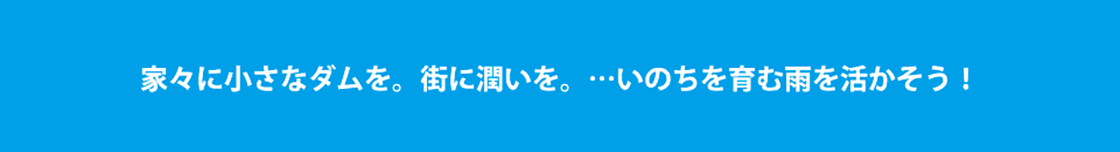2022.07.02
下町×雨・みどりWS第1回 『「水」がつくったまち「すみだ・向島」を探る』報告
下町×雨・みどりプロジェクト担当
下町すみだのまちの雨の行方を辿りながら、私たちにできる小さな気候変動対策を考えるプロジェクトの活動が始まりました。
第1回目ワークショップは、4月29日(金・祝)に雨の中、佐原滋元さん(雨水市民の会理事・向島学会)の案内で工場が多い墨田区八広・東墨田(墨田区向島地区のこの辺りは「吾嬬」と呼ばれていました)を旧中川まで、雨とまちとの関係を歴史の変遷を辿って歩きました。その後、たから会館(墨田区京島にある地域集会所)で佐原さんから水に関わる「すみだ・向島」の歴史と地理の説明を聴きました。

吾嬬のまちを歩く
吾嬬は戦前から紡績、石鹸、肥料などの大工場があり、そこに働く人たちが暮らしたまちでした。縦横無尽にめぐる川や水路を活かして船で資材や製品を運んでいました。水路は自然の高低差を使って水の流れのようにくねくねして、今もその面影を残しています。運送手段が車に代わり、川や水路は役目を終えて道路となっています。昔あった大工場が移転して、団地となったところや今回は雨で行かれなかった旧中川上流部と荒川をの境にある木下川(きねがわ)水門(地図の右上)は、ゼロメートル地帯のまちを守るため水位を荒川より常に1m低くするようにポンプで荒川に排水しているそうです。旧中川の下流部は再び荒川に合流する地点には「閘門」という船が出入りできるように水位差を調整する水門があり、その差は最高3mもあるそうです。春には河津桜が咲く土手は高く、地盤沈下によりまち全体が低いことを実感できます。また、墨田清掃工場がある広い敷地は、元は大きな肥料工場があったそうです。まち歩きの終点は京島のたから会館で、歩いたところの振り返りをしてから、長くすみだに住んで歴史や地理にも詳しい佐原さんの話を聞きました。

(左)ワークショップ第1回目は、雨の中、まち歩きに出発!
(中)旧中川の土手はかなり高い。ボートの練習風景が見られた。
(右)木造住宅が密集するまちは長い年月をかけて防災に強いまちへ変身している。
水がつくったすみだ・吾嬬の歴史

京島のたから会館で佐原滋元さんの講座を聴いた。ウエブの参加者もいた。
まち歩きの後に、たから会館で佐原さんの講座があり、ウエブで参加された方もいらっしゃいました。
佐原さんは、生まれ育ちも向島で当会の理事です。NPO法人向島学会にも所属され、まちを知り尽くしている方です。今回の話は、”水も滴るいい男”の話と冗談も織り交ぜながら楽しく聞かせてもらいました。すみだは四方を川に囲まれ、かつては洪水による被害が多かった地域です。
大昔はこの辺りは海でした。大河が運ぶ土砂で陸地となりましたが、湿地帯で人が住める所ではありませんでした。室町時代には向島地域のいくつかの聚落名が見られ、農業が細々と営まれていたようです。
江戸時代には、利根川の東遷により合流していた荒川も入間川に付け替えられ、新しく葛西用水などが整備され、大規模な農地開発がされました。また、明暦の大火(1657)を契機に江戸の都市計画が始まり、その一環で本所地域は堀割を掘削し、その土砂で埋め立て、まちを広げていきました。人々が生活する上での水の確保のため亀有上水(本所上水ともいう)が開削されましたが、その後メンテナンスの問題*や井戸の普及のため、曳舟川となり、農業用水や物資の船搬送のために中居堀、北十間川も開削されました。江戸時代中期には、江戸の庶民の生活も安定し、この地域では梅林もあちこちに造られて花見を楽しんだり、神社仏閣を参拝する人たちが通る参道も賑わいました。
*亀戸上水は江戸の六上水(他神田上水・玉川上水・青山上水・三田上水・千川上水)の一つだったが、1722年に青山・三田・千川上水と共に廃止された。その理由はメンテナンスにお金がかかるということだが、亀戸上水は他に水が来ない時が多かった。玉川上水は100mを流す高低差が21cmであったが、亀戸上水は2.3cm/100mしかなかった。
明治になり、1888年町村制が実施され、三つの村と亀戸の一部が吾嬬村となりました。以前からたびたび洪水が起きていましたが、この頃から墨東地域には紡績、皮革、化学など工場が集積してきて、1910年(M43)の大洪水は水が1カ月も引かず甚大な被害を与えました。国家的事業として1911(M44)年から荒川放水路の開削事業が始められ、20年の歳月をかけ完成しました。1923(T12)の関東大震災は吾嬬地域の被害は比較的少なかったのですが、本所地域などで被災した工場が移転するなどして、工場の一大集積地となっていきます。また、工場に働く労働者や家族も住み、商店街や映画館などの娯楽施設、念願のポンプ場も完成し、賑わいのあるまちとなっていきました。しかし、工場のまちであることは軍需工場の集積地と見なされて、東京大空襲(1945)では重点的に爆撃を受けることになりました。
まちづくりについても議論
●京島地域はアーティストたちがリノベーションなどのまちづくりをしていると聞いていますが、その実態は?