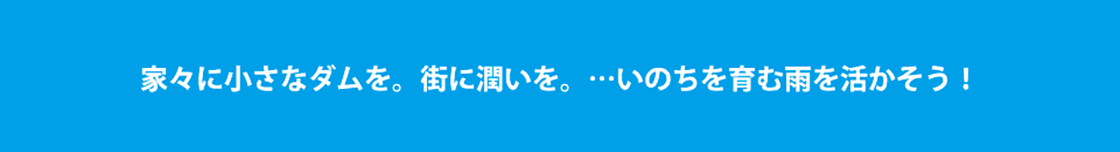2021.07.01
第二回気候変動と雨水活用シンポジウム 開催報告
小川幸正(雨水市民の会理事・NPO雨水まちづくりサポート理事)

当日の様子:ZOOMウェビナー方式にて実施
2021年5月13(木)、第二回気候変動と雨水活用シンポジウム「雨水活用の普及と基準や制度を考える」が開催されました。主催は、昨年の第一回と同じく、法政大学エコ地域デザイン研究センター、一般社団法人日本建築学会あまみず活用の評価を考える小委員会、公益社団法人雨水貯留浸透技術協会、特定非営利活動法人雨水まちづくりサポートの4団体に、雨水基準制度研究会を加えた5団体による共催で実施されました。シンポジウムは、コロナ禍のなか緊急事態宣言を受けて完全リモート方式で実施しました。
【シンポジウム】
シンポジウムはZOOMウェビナー方式で行われ、参加登録者数は270名で、開催中の最大参加数は250名でした。リモート方式なので、地域も全国からの参加がありました。昨年の第一回の際は法政大学のホールをお借りして130名ほどの参加者数でしたが、今回大きく増えた要因としては、リモート方式によること以外にも、この1年で気候非常事態宣言やグリーインフラの盛り上がり、流域治水プロジェクトなど、国策レベルでの雨水を取り巻く社会情勢が大きく変化したことによる関心の高まりがあったと感じられました。
リモート方式としたことで、シンポジウムの構成を二部に分け、第一部は事前動画配信としました。第二部はパネルディスカッションを主としてコンパクトに納めました。リモートによる一般参加者はQ&Aで議論に参加してもらいました。私は特別報告の発表とパネルディスカッションに登壇しました。
第一部 事前収録・事前配信
・挨拶:国土交通省水資源部水資源政策課長 藤川眞行
・開催趣旨説明:NPO雨水まちづくりサポート理事長 神谷 博
・基調講演1:「気候変動を踏まえた都市浸水対策と雨水の活用」/古米弘明(東京大学教授)
・基調講演2:「ドイツにおける気候変動適応策とSDGsの動向」/ パスカル・グードルフ氏(ECOS JAPAN西日本事務所代表)
・特別報告:「欧州における雨水活用規格の動向」/小川幸正(NPO雨水まちづくりサポート副理事長)
・報告1「雨水活用の計画と設計」/向山雅之(竹中工務店)
・報告2「雨水活用の水量と水質」/岡田誠之(東北文化学園大学名誉教授)
・報告3「雨水活用の製品技術」/屋井裕幸(雨水貯留浸透技術協会常務理事)
第二部 当日会場報告
・趣旨説明/神谷 博(NPO雨水まちづくりサポート理事長)
・報告要旨1「雨水活用の計画と設計」/向山雅之(竹中工務店)
・報告要旨2「雨水の水量と水質」/岡田誠之(東北文化学園大学名誉教授)
・報告要旨3「雨水の製品技術」/屋井裕幸(雨水貯留浸透技術協会常務理事)
・パネルディスカッション/「雨水基準・制度の目指す方向性」
登壇者:向山雅之、岡田誠之、屋井裕幸
コメンテーター:古米弘明、パスカル・グードルフ、小川幸正、村川三郎、笠井利浩、福岡孝則
コーディネーター:神谷 博
【成果】
シンポジウムの構成を二部に分けたことにより、第二部のパネルディスカッションを主として議論を深めることができました。登壇者以外の参加者もQ&Aで議論に参加し、活発な意見交換を行うことができました。この1年の活動で準備した「雨を活かす」(概要版・素案)ならびに「雨水活用の手引き」(素案)を示し、皆さんの意見を求めました。また、シンポジウム後に始める第2期の雨水基準制度研究会への参加を呼び掛けました。さらに、シンポジウムへの参加登録時と終了後にアンケートを実施し、第二期の活動に向けた準備を整えることができました。こうした活動により、雨水活用の民間基準を整え、自治体の雨水施策の制度整備に寄与したいと思います。雨水市民の会の会員の皆さまにも、雨水基準制度研究会の活動への支援や参加をお願いします。
なお、雨水まちづくりサポートで本シンポジウムの報告書を作成中です。
【本件の問合せ先】
雨水基準制度研究会の事務局:NPO 雨水まちづくりサポート E-mail: amemachi.supo@gmail.com