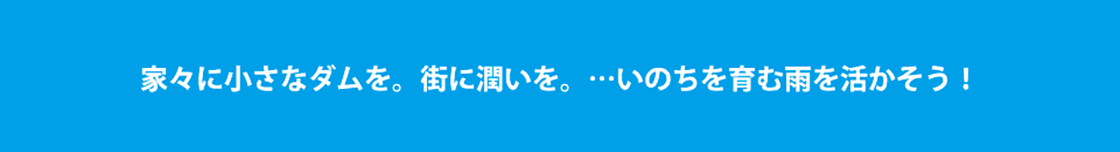2018.10.14
〜その2〜 基調講演「気象災害の犠牲者はなぜ減らないのか」
Webあまみず編集委員
(第11回雨水ネットワーク全国大会 2018 in 東京 レポート)
「気象災害の犠牲者はなぜ減らないのか」
三隅良平氏(国立研究開発法人防災科学研究所 水・土砂防災研究部長)

基調講演で気象災害の予測と避難方法の問題点を講演された三隅良平氏
三隅氏は、記憶に新しい西日本を中心に大きな被害があった「平成30年7月豪雨」(死者220名、行方不明者9名(消防庁・2018/7/31現在))を例に、25年前に発生した長崎豪雨(1回の災害で同規模の犠牲者が出た)と比較して、この間、天気予報の精度が向上し、市民が気象情報を知る機会も確実に増え、なぜ、犠牲者が減らないのかについて講演されました。
●災害発生の予報:広範囲で大雨が降る予報は当たるが、狭い地域に降る大雨はどこにどれだけ降るのかの予報が難しい。
●地方自治体の災害対応:避難勧告や避難指示は市町村が指示することになっている。市町村では1時間ごとに気象情報を整理する決まりになっていて、急激な気象条件の変化に対応できていない。また、災害発生時に市町村に住民やマスコミからの問い合わせが殺到し、災害対策機能が失われてしまうこともある。
●水害避難の難しさ:水害発生時に自宅から避難所に向かう経路で濁流に飲まれた、避難所そのものが水没してしまったなどの実例をあげ、それぞれ土地の環境によって避難の方法は異なってくるので、事前に行政と住民が良く話し合って、整理しておかなければならない。
●住民の防災意識:激しい気象の発生を事前に予測することは非常に困難である。「まさかこんなことが起こるとは」と後から思うのでは遅い。自分が住んでいる場所のハザードマップや昔の地図、過去の災害などを調べ、稀にしか発生しない気象の発生も想定し、どのような被害を受けるか、また、ライフラインが遮断されたときの想定もしておくことが必要である。
第11回雨水ネットワーク全国大会 2018 in 東京 〜その1〜