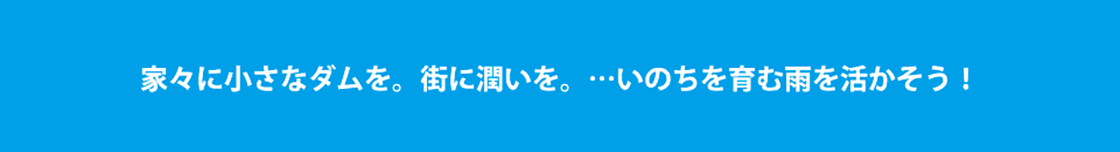2025.02.08
(10) すみだの雨水活用をみてみよう 〜エクスカーション
雨水ネットワーク全国大会 in すみだ実行委員会
“第14回雨水ネットワーク全国大会2024 in すみだ”報告 (その10)
8月4日午後、この大会の最後は3つのコースで「すみだ」を体感してもらうエクスカーションです。合計49名が参加しました。
A:たもんじ交流農園と多聞寺−都市の中の緑化と水循環を知り、活動の担い手と交流する
案内者:墨田区観光協会ガイド、寺島・玉ノ井まちづくり協議会、多聞寺 岸田住職、武蔵野大学(橋本淳司氏、学生)
コース:(バス移動)水神前→隅田川神社(隅田川総鎮守)→木母寺(梅若の涙雨)→梅若橋(御前菜畑・隅田川御殿)→多聞寺(雨水利用)→たもんじ交流農園→現地解散

左)木母寺で「梅若の涙雨」を解説する墨田区観光協会ガイド 中)雨水寺と呼ばれる多聞寺の岸田住職 右)たもんじ交流農園でワークショップをする武蔵野大学学生と橋本淳司氏
まずは墨田区観光協会ガイドの案内で、白鬚防災団地を抜け、隅田川沿いの史跡、隅田川神社(江戸時代はのちに訪れる多聞寺が別当寺だった)、梅若伝説が伝わる木母寺、さらに江戸時代に将軍に献上する野菜が作られた御前菜畑を訪れました。たもんじ交流農園で育てられている江戸野菜「寺島ナス」も作られていたでしょう。
多聞寺は、1996年に境内2箇所に合計21トンの雨水タンクを設置し、トイレ、墓参用水、散水に使っています。岸田正博(しょうはく)住職は「トイレにも水道を使うのはもったいない。山奥に巨大なダムを作って、雨を下水に流し込むのは都会のエゴだ」と雨水利用をした経緯を話されました。30年近く経って雨水活用の設備も古くなり、最近ポンプを新しく取り替えられたそうです。
たもんじ交流農園は多聞寺と地続きの場所にあります。寺島・玉ノ井まちづくり協議会が寺から無償で土地の提供を受け、2017年からガバメントクラウドファンディングにて農園整備を行いました。多聞寺の雨水タンクのオーバーフローや隣接する家屋から雨水をもらいうけ、さらに井戸を掘って農園の水やりやほたるのすみかづくりにも挑戦しています。暑い日差しをネットで遮ったウッドデッキで、武蔵野大学の学生と橋本淳司氏がワークショップを行いました。雨水を浸透しやすいものは何か?この農園から探すことがテーマでした。実際にスポンジとジョウロを使い実験も行いました。参加者はお土産に寺島ナスを1個収穫することができました。
B:両国ポンプ所と両国国技館周辺−大規模雨水利用の始まりと雨水排水の現場を訪ねる
案内者:東京都下水道局、佐原滋元(雨水市民の会)
コース:(バス移動)両国駅→両国国技館→両国ポンプ所内部見学→旧安田庭園(汐入の池)→隅田川沿い水門→現地解散

左)両国ポンプ所の5.25mある流入管の実物大の写真の前で説明を聞く 中)安田庭園の汐入回遊式庭園を歩く 右)隅田川沿いにある両国ポンプ所の放流ゲート
両国駅西口にある両国江戸NORENの中にある観光案内所に集合し、雨水市民の会の佐原滋元氏が両国国技館の雨水活用について説明をしました。そこから両国ポンプ所へ移動しました。
両国ポンプ所は、東京都下水道局東部第一下水道事務所の丸山氏がまず施設の概要の説明をされました。両国ポンプ所は2002年4月に完成、敷地9000㎡、排水面積421ha(墨田区全体の面積の約1/3)、計画降雨規模は1時間あたり50mmの雨水を排除する能力があります。通常は無人で運転され、木場ポンプ所から遠隔操作を行なっています。稼働回数は年間10回ほど、ポンプ楊程25m、流入管の直径は5.25m、ポンプ排水能力は毎秒59㎥、動力は飛行機のエンジンに用いられているガスタービンを使用しています。ガスタービンに使う燃料の備蓄容量は166kLで、稼働状況にもよるが約18時間ポンプ排水が可能とのことでした。墨田区南部は、かつて浸水が頻発しており、両国ポンプ所は浸水被害の解消に大きな役割を果たしています。
ポンプ所見学後は、安田庭園へ移動。途中、東京都慰霊堂(伊東忠太設計)とその屋根に設置された妖怪のようなキャラクター「レイレイ」について佐原氏より説明がありました。かつては隅田川の水を引き込んだ汐入回遊式庭園だった安田庭園を抜け、隅田川沿いにある両国ポンプ所の放流口まで足を延ばしました。放流ゲート地点の管渠の大きさは幅3m、高さ4mが2つ連なっています。また隅田川の対岸に見えたゲートについて後日調べたところ、元浅草幹線(幅4.8m、高さ2.5m)の放流口であることがわかりました。
C:東京ソラマチ・スカイツリー−墨田区最大の雨水活用スポットを訪ね、環境配慮の取り組みを見学する
案内者:東武タウンソラマチ株式会社
コース:都営浅草線「押上駅」改札口前→ソラマチタウン地下1階雨水貯留槽→1階・4階のスカイアリーナ周辺の植栽→1階防潮板→地下2階中水機械室→上水受水槽→1階で解散

上)東京ソラマチ・スカイアリーナの植栽 下左)地下駐車場の雨水貯留槽マンホール 下中)雨水ろ過装置 下右)塩素注入装置(消毒用)
限られた時間の見学で、雨水利用施設の主要な施設のみを見学しました。雨水利用と中水利用のシステムは次のとおりです。
⚫︎雨水利用:屋上等の雨水→沈砂槽→雨水貯留槽*(2635㎥:雨水利用のために800㎥及び流出抑制のために1835㎥)→砂ろ過装置→塩素消毒→雑用水槽**→植栽散水
* 雨水貯留槽が満水時には雨水竪管に切り替えバルブがあり、直接下水道に排水している。
**雨水の雑用水槽からも水洗トイレ洗浄水として送水できるようになっている。
⚫︎中水利用:冷却塔ブロー水と加湿ドレン水→貯留槽→砂ろ過装置→pH調整→塩素消毒→雑用水槽→水洗トイレ洗浄水
今回、雨水利用施設の見学ができて貴重な機会でした。しかし、スタッフを含め20名の多人数だったことと、時間的制約があり、具体的な話が聞けませんでした。雨水貯留槽の容量は単一民間施設としては最大級です。用途は植栽のみですが、流出抑制効果を含め、この施設の機能や効果は注目に値します。過去の発表されたデータでは、トイレや植栽散水等の雑用水は雨水と冷却塔ブロー水でその10%程度を供給しているとのことです。
” 第14回雨水ネットワーク全国大会2024 in すみだ”報告 リンク
(1)雨を活かして、未来へつなごう。〜”第14回雨水ネットワーク全国大会2024 in すみだ”に2200人が集まった
(2)すみだの雨水〜過去から学び、Next Stageへ〜(セッションⅠ)
(3)雨とネイチャーポジティブ〜雨水を活用した都市緑化の可能性ー立体的緑地と平面的緑地による生物多様性の回復(セッションⅡ-1)
(4) ゼロメートル地帯から考える雨と防災(セッションⅡ-2)
(5) くらしの中の雨水〜見える、楽しむ、活かす(セッションⅡ-3)
(6) 飲む雨水〜インフラとヒトの変化から考える飲むあまみずの近未来(セッションⅡ-4)
(7) セッションⅡ-分科会「雨水と私たちの未来」まとめ
(8) 雨水は世界を救うか?(セッションⅢ)
(9) すみだ雨水宣言2024
本ページ (10) すみだの雨水活用をみてみよう〜エクスカーション
(11) 楽しく雨を体験 〜あまみずフェスティバル
2024年8月3〜4日に開催された第14回雨水ネットワーク全国大会2024 in すみだは「雨水ネットワーク全国大会 in すみだ実行委員会」および墨田区が主催して行いました。実行委員は、地元団体のNPO法人雨水市民の会、NPO法人寺島・玉ノ井まちづくり協議会、中央大学、千葉大学、合同会社アールアンドユー・レゾリューションズ、雨水ネットワーク事務局の公益社団法人雨水貯留浸透技術協会など、18名のメンバーで構成。墨田区は大会会長として山本亨墨田区長、区役所事務局として環境政策課が参加しました。