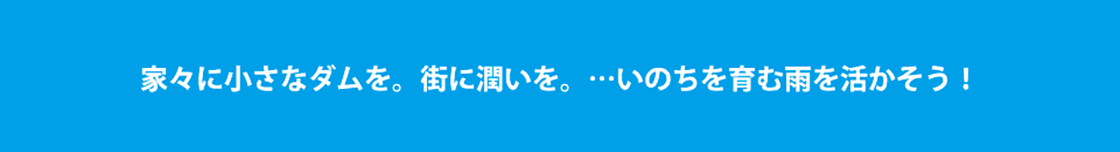2025.02.08
(7) セッションⅡ 分科会「雨水と私たちの未来」まとめ
雨水ネットワーク全国大会 in すみだ実行委員会
“第14回雨水ネットワーク全国大会 in すみだ”報告(その7)
 8月3日の最後は、セッションⅡにおける4人のコーディネーターが各分科会の報告をしました。その後、山本耕平実行委員長がコーディネーターを務め、フロアを交えたディスカッションをしました。
8月3日の最後は、セッションⅡにおける4人のコーディネーターが各分科会の報告をしました。その後、山本耕平実行委員長がコーディネーターを務め、フロアを交えたディスカッションをしました。
⚫︎セッションⅡ-1
雨とネイチャーポジティブ 〜雨水を活用した都市緑化の可能性
−立体的緑地と平面的緑地による生物多様性 コーディネーター:霜田亮祐
⚫︎セッションⅡ-2
ゼロメートル地帯から考える雨と防災 コーディネーター:菜原 航
⚫︎セッションⅡ-3
くらしの中の雨水〜見える、楽しむ、活かす コーディネーター:笹川みちる
⚫︎セッションⅡ-4
飲む雨水〜インフラとヒトの変化から考えるあまみずの未来 コーディネーター:山村 寛
Q 雨庭について、墨田区のような土地が狭く水がしみこみにくいところでの方法はどのようなものがありますか?
→有効な手法として、雨樋プランターのような立体的な雨庭というアイデアがあります。
Q 雨水活用が機能を求めるだけではなくて、幸福感、楽しみを感じる取り組みとは?
→雨水活用と緑は親和性が深く、緑と一緒に進めれば楽しさは大きく増します。植物に触れることはとても大事です。
Q 防災に対して雨水活用のこれからの方向性は?
→防災は積み重ねが大事です。雨水タンクの数を増やすことは防災にとって大いに意義があります。タンクの貯水量を見える化し、行政から豪雨の前にはタンクを空けるように呼びかけるなど、防災に寄与するようなシステムが必要です。
Q 家庭用のタンクは大きすぎて移動ができない。天水尊のような200リットルという家庭用タンクの容量は適切なのでしょうか?
→利用目的に応じて容量は選択すべきですが、貯水量と使いたい量とのバランスを取るのは難しいです。天水尊は防災という目的から200リットルになったのではないでしょうか。
Q 「雨水を飲む」ためには意識をどう変えるかが大事ではないでしょうか?
→教育、啓発が重要で、そのための手法をいろいろと工夫していく必要があります。インフルエンサーとのコラボなど、さまざまなメディアで発信していくべきではないでしょうか。8月1日からこの会場の外の広場で「あまみずフェスティバル」が開催され、そこで雨水を飲む体験ができます。よろしければ体験してください。
Q 行政からもいろいろ情報発信すべきではないでしょうか?
→東京都などが大気汚染のデータにもとづいて降水の汚れ具合の予測情報を出し、共有できるようにするのも有効です。
Q 墨田区では古いタンクが多いのでリニューアルが必要です。
→修理業者等も少なく、修理を促すような仕組みができていません。リニューアルする場合には、水質を高めたりろ過機能を組み込んだり、雨水を飲むためのバージョンアップしたタンクに入れ替えていくことが望まれます。

セッションⅡが終了後、同じフロアーで交流会が行われた。地元の食べ物や文京区産雨水で作った「雨水ビール」が振る舞われた。
” 第14回雨水ネットワーク全国大会2024 in すみだ”報告 リンク
(1)雨を活かして、未来へつなごう。〜”第14回雨水ネットワーク全国大会2024 in すみだ”に2200人が集まった
(2)すみだの雨水〜過去から学び、Next Stageへ〜(セッションⅠ)
(3)雨とネイチャーポジティブ〜雨水を活用した都市緑化の可能性ー立体的緑地と平面的緑地による生物多様性の回復(セッションⅡ-1)
(4) ゼロメートル地帯から考える雨と防災(セッションⅡ-2)
(5) くらしの中の雨水〜見える、楽しむ、活かす(セッションⅡ-3)
(6) 飲む雨水〜インフラとヒトの変化から考える飲むあまみずの近未来(セッションⅡ-4)
本ページ (7) セッションⅡ-分科会「雨水と私たちの未来」まとめ
(8) 雨水は世界を救うか?(セッションⅢ)
(9) すみだ雨水宣言2024
(10) すみだの雨水活用をみてみよう〜エクスカーション
(11) 楽しく雨を体験 〜あまみずフェスティバル
2024年8月3〜4日に開催された第14回雨水ネットワーク全国大会2024 in すみだは「雨水ネットワーク全国大会 in すみだ実行委員会」および墨田区が主催して行いました。実行委員は、地元団体のNPO法人雨水市民の会、NPO法人寺島・玉ノ井まちづくり協議会、中央大学、千葉大学、合同会社アールアンドユー・レゾリューションズ、雨水ネットワーク事務局の公益社団法人雨水貯留浸透技術協会など、18名のメンバーで構成。墨田区は大会会長として山本亨墨田区長、区役所事務局として環境政策課が参加しました。